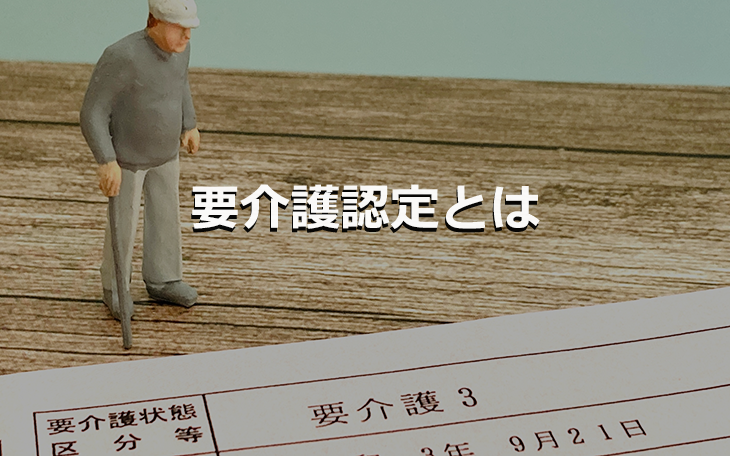介護が必要になったとき、適切なサービスを受けるために欠かせないのが「要介護認定」制度です。この制度を正しく理解すれば、介護サービスをスムーズに利用でき、介護する家族の負担軽減にもつながります。
本記事では、要介護認定の基本的な仕組みから具体的な申請方法、認定基準、利用開始までの流れをわかりやすく解説していきます。
要介護認定の概要
制度の目的と意義
要介護認定とは、介護保険制度の中核をなす仕組みで、高齢者や障がい者が日常生活を営む上でどの程度の介護が必要かを客観的に判定する制度です。2000年に介護保険制度が開始されて以来、多くの高齢者とその家族にとって重要な社会保障制度となっています。
この認定を受けることで、介護保険サービスを利用する際の自己負担額が軽減され、専門的な介護サービスを受けることができるようになります。具体的には、介護サービスの利用にかかる費用は、原則として1割から3割程度の自己負担となります。負担額は所得や認定の内容に応じて決まり、高齢者本人が住民税非課税世帯の場合は自己負担割合が1割に設定され、所得が高い場合は3割に設定されることがあります。
この制度により、介護を受ける高齢者は必要なサービスを受けやすくなり、家族介護の負担を軽減できます。また、地域における高齢者の生活の質を保つための支援にもつながります。
対象者について
要介護認定の対象者は、原則として次の2つに分けられます。
- 第1号被保険者:65歳以上の方が該当します。
- 第2号被保険者:40歳から64歳までの方が、加齢に伴う特定の病気(特定疾病)によって介護が必要となった場合に該当します。具体的な特定疾病には、がん(末期)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺など、16の特定疾病(※)が含まれます。
※16の特定疾病 – 厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」
要介護認定の区分と認定基準
要介護認定は、心身の状態や日常生活で必要な支援の程度によって、軽度から重度まで7段階に分かれます。その中で「要支援」と「要介護」に大別されています。
要支援1・要支援2
自立して生活できる部分が多いものの、将来の悪化を防ぐために軽い介助や生活支援が必要な段階。買い物や掃除、入浴など、一部の動作に手助けがあれば生活できる状態です。
要支援1
基本的な日常生活はほぼ自分で行えるものの、複雑な動作には一部支援が必要な状態です。掃除や買い物などの手段的日常生活動作に軽微な困難がある程度で、適切な支援により機能の維持・改善が期待できる状態です。
要支援2
要支援1よりもやや支援が必要な状態で、立ち上がりや歩行が不安定で、排泄や入浴などにも一部介助が必要になることがあります。しかし、予防的な支援により機能の維持・改善の可能性があります。
要介護1~要介護5
要介護度は数字が大きくなるほど、身体的・精神的な機能が低下し、必要な介護の量や種類が増えていきます。 「要支援」が予防を目的とした軽度の支援であるのに対し、「要介護」は、すでに介助が必要な状態であるという違いがあります。この要介護度によって、利用できる介護サービスの種類や量(支給限度額)も変化します。
要介護1
要支援2より状態が悪化し、部分的な介護が必要な状態です。立ち上がりや歩行が不安定で、排泄や入浴などの基本的日常生活動作に一部介助が必要になります。理解力の低下もみられることがあります。
要介護2
軽度から中等度の介護が必要な状態で、立ち上がりや歩行が自力では困難になり、排泄・入浴・衣服の着脱などに介助が必要です。問題行動や理解の低下もみられることがあります。
要介護3
中等度の介護が必要な状態で、立ち上がりや歩行が自力でできず、排泄・入浴・衣服の着脱に全面的な介助が必要になります。いくつかの問題行動や理解の低下もみられます。
要介護4
重度の介護が必要な状態で、日常生活能力がかなり低下し、排泄・入浴・衣服の着脱に全面的な介助が必要です。多くの問題行動や全般的な理解の低下もみられます。
要介護5
最重度の介護が必要な状態で、日常生活全般にわたって全面的な介助が必要になります。多くの問題行動や全般的な理解の低下に加え、意思疎通が困難になることもあります。
認定基準の詳細
認定基準は、厚生労働省が定めた「要介護認定等基準時間」に基づいて決定されます。これは、介護に要する時間を分単位で算出したもので、以下のような基準となっています。
- 要支援1:25分以上32分未満
- 要支援2・要介護1:32分以上50分未満
- 要介護2:50分以上70分未満
- 要介護3:70分以上90分未満
- 要介護4:90分以上110分未満
- 要介護5:110分以上
ただし、認定審査会では時間だけでなく、認知症の症状や医学的な状態なども総合的に判断されます。
申請から通知までの流れ
申請手続きの詳細
要介護認定の申請は、住所地の市区町村役場の介護保険課または地域包括支援センターで行います。申請に必要な書類は以下の通りです。
- 要介護・要支援認定申請書:市区町村の窓口やホームページで入手可能
- 介護保険被保険者証:65歳になると自動的に交付される
- 医療保険被保険者証:40~64歳の第2号被保険者のみ必要
- マイナンバーカードもしくはマイナンバーが確認できるもの
- 診察券など主治医の情報が確認できるもの
申請は本人または家族が行うのが一般的ですが、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設に代行を依頼することも可能です。
認定調査の実施
申請後、市区町村の職員または委託された介護支援専門員(ケアマネジャー)による認定調査が実施されます。調査は原則として申請者の自宅で行われ、以下の項目について詳細に確認されます。
基本調査
身体機能・生活機能(麻痺・関節可動域、移乗・移動、排尿・排便、口腔清潔、食事摂取、衣服の着脱など)、認知機能(意思の伝達、記憶、理解など)、精神・行動障害(問題行動の有無と頻度)、社会生活への適応(薬の管理、金銭の管理、電話の利用など)について調査されます。
特記事項
基本調査だけでは把握できない介護の手間や特別な医療処置の必要性などが記録されます。
調査時間は通常1時間程度で、できるだけ普段の状態を正確に伝えることが重要です。
主治医意見書の取得
認定調査と並行して、主治医による意見書が作成されます。かかりつけ医がいない場合は、市区町村が指定する医師による診察を受ける必要があります。
主治医意見書には、疾病・負傷の状況、ADL(日常生活動作)・認知機能・精神症状に関する意見、医学的管理の必要性、介護認定審査会に対する意見などが記載されます。
介護認定審査会での審査
認定調査結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会で要介護度が決定されます。審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者5名で構成され、申請者一人ひとりについて慎重に審査されます。
審査では、一次判定結果(コンピュータによる判定)を基準としつつ、特記事項や主治医意見書の内容を総合的に検討し、最終的な要介護度を決定します。
要介護認定の結果通知と介護サービスの利用開始
審査の結果は、通常申請から1ヶ月ほどで「認定通知書」として本人やご家族に届きます。通知書には認定区分のほか、利用可能な介護サービスの案内も記されています。
認定区分に応じて、訪問介護や通所介護(デイサービス)、ショートステイ、施設入所サービスなどが利用可能です。利用にあたっては介護支援専門員がケアプランを作成し、申請者の生活に合ったサービスの調整を行います。
要介護認定の有効期限と更新手続き
認定の有効期限
要介護認定には有効期限があります。
- 新規申請:原則として6ヶ月です。(利用者の心身の状態に応じて、3~12ヶ月の範囲で設定されることもあります。)
- 更新申請:原則として12ヶ月です。(利用者の心身の状態に応じて、3~48ヶ月の範囲で設定されることもあります。)
有効期限は認定結果通知書に明記されており、期限が切れる前に更新申請を行う必要があります。期限切れとなった場合、介護保険サービスの利用に支障が出る可能性があるため、注意が必要です。
更新申請の手続き
更新申請は、有効期限の60日前から申請可能です。手続きは新規申請とほぼ同様で、認定調査や主治医意見書の作成が再度行われます。
更新時には、前回認定時からの状態変化が重点的に調査されるため、日頃から状態の変化を記録しておくことが重要です。
要介護認定の区分変更申請について
有効期限前であっても、状態が大きく変化した場合は区分変更申請を行うことができます。例えば、転倒により骨折して介護度が重くなった場合や、リハビリにより状態が改善した場合などが該当します。
区分変更申請も新規申請と同様の手続きが必要で、認定されれば新しい認定の効力は申請日に遡って発生します。
まとめ
要介護認定は、高齢者が安心して生活を続けるための重要な制度です。制度を正しく理解し、適切なタイミングで申請を行うことで、本人にとっても家族にとっても大きな支援となります。
申請には時間がかかるため、介護が必要になりそうな兆候が見られたら、早めに地域包括支援センターなどに相談することをお勧めします。また、認定後も定期的な見直しを行い、状態に応じた適切なサービスを受けることが大切です。
介護は決して一人で抱え込むものではありません。要介護認定制度を活用し、専門的なサポートを受けながら、本人らしい生活を維持していくことが重要です。制度について不明な点があれば、遠慮せずに市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談しましょう。